2023年03月26日 夕方公開終了
向坂くじら(さきさか・くじら)
向坂くじら(さきさか・くじら)
2016年、Gt.クマガイユウヤとの詩の朗読とエレキギターのパフォーマンスユニット「Anti-Trench」として活動開始。詩と朗読を担当する。TBSラジオ「アフター6ジャンクション」、谷川俊太郎トリビュートライブ「俊読」など、多数出演。2021 年、Anti-Trenchファーストアルバム「ponto」「s^ipo」二枚同時発売。同年、びーれびしろねこ社賞大賞を受賞。2022年、第一詩集『とても小さな理解のための』(しろねこ社)を刊行。同年、埼玉県桶川市にて「国語教室 ことぱ舎」を創設。慶應義塾大学文学部卒。





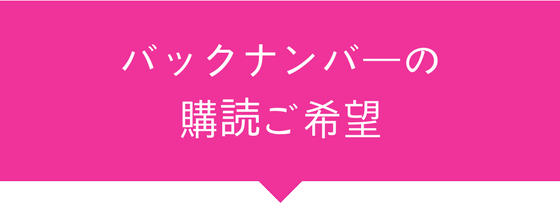


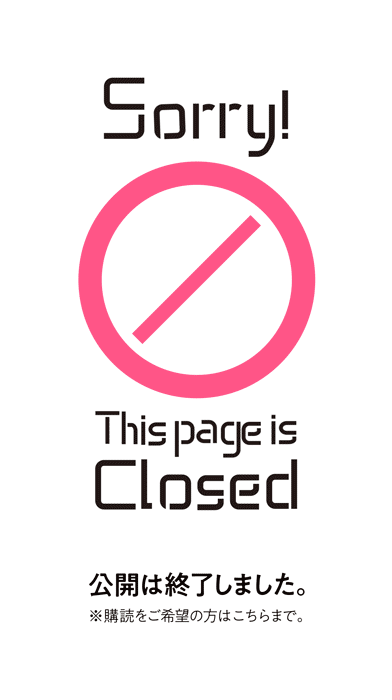
しーなま (@shiinama)
12-「そっちでいくのかよ」 https://t.co/0u2Iwil2mw